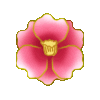日本各地に祀られている神様のご紹介。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日本の水の女神を代表する実力派。
タカオカミ神は、日本神話に登場する女神で、全国に広がる貴船神社(総本社は京都の貴船神社)の祭神であることから、貴船神とも呼ばれてその名を知られている、代表的な水の女神である。
水の神は、女性と決まっているわけではないが、日本の場合は女神としてイメージされる場合が多い。
古来、水にかかわる神霊の代表格といえば龍蛇神である。
民話や民間信仰でもおなじみの龍や蛇は水の精霊であったり、水をつかさどる神霊の化身であったりする。
こうして龍や蛇は、農耕と深くかかわる豊穣の大地母神として信仰されてきた。
そこからの連想として、女神のイメージが形成されたと考えられる。
飛び散る火の神の血から化成。
日本神話では、「神生み」の物語の最後にイザナギ命が火の神カグツチの首をバッサリと断ち斬ったとき、流れた鮮血から化成した水の神であるとされている。
『古事記』や『日本書紀』一書第六には、イザナギ命が火の神カグツチの首を斬ったときに、飛び散った血からクラオカミ神が生まれたとあり、また『日本書紀』一書第七にはタカオカミ神が生まれたとある。
名義について考えてみると、タカオカミの「高」は高い峰・天の高みといった意味で、そこにあって雨水をつかさどる神としての雷神が思い浮かぶ。
一方クラオカミの「闇(くら)」は、鬱蒼とした緑に覆われ、昼なお暗い渓谷を連想させ、峰から下る
渓流に宿る水神という性格がうかがわれる。
山に降った雨は、谷を下って川となり、野を潤すという意味で、二神を合わせて源流の神と考えることができる。
「龗(おかみ)」とは、雨(水)をつかさどる龍神のことである。
タカオカミ神は、クラオカミ神と一緒に神社の祭神とされていたり、あるいは二神を総称した「淤加美神(おかみのかみ)」の名で祀られている場合もある。
タカオカミ神は、日本神話に登場する女神で、全国に広がる貴船神社(総本社は京都の貴船神社)の祭神であることから、貴船神とも呼ばれてその名を知られている、代表的な水の女神である。
水の神は、女性と決まっているわけではないが、日本の場合は女神としてイメージされる場合が多い。
古来、水にかかわる神霊の代表格といえば龍蛇神である。
民話や民間信仰でもおなじみの龍や蛇は水の精霊であったり、水をつかさどる神霊の化身であったりする。
こうして龍や蛇は、農耕と深くかかわる豊穣の大地母神として信仰されてきた。
そこからの連想として、女神のイメージが形成されたと考えられる。
飛び散る火の神の血から化成。
日本神話では、「神生み」の物語の最後にイザナギ命が火の神カグツチの首をバッサリと断ち斬ったとき、流れた鮮血から化成した水の神であるとされている。
『古事記』や『日本書紀』一書第六には、イザナギ命が火の神カグツチの首を斬ったときに、飛び散った血からクラオカミ神が生まれたとあり、また『日本書紀』一書第七にはタカオカミ神が生まれたとある。
名義について考えてみると、タカオカミの「高」は高い峰・天の高みといった意味で、そこにあって雨水をつかさどる神としての雷神が思い浮かぶ。
一方クラオカミの「闇(くら)」は、鬱蒼とした緑に覆われ、昼なお暗い渓谷を連想させ、峰から下る
渓流に宿る水神という性格がうかがわれる。
山に降った雨は、谷を下って川となり、野を潤すという意味で、二神を合わせて源流の神と考えることができる。
「龗(おかみ)」とは、雨(水)をつかさどる龍神のことである。
タカオカミ神は、クラオカミ神と一緒に神社の祭神とされていたり、あるいは二神を総称した「淤加美神(おかみのかみ)」の名で祀られている場合もある。
PR
 Comment
Comment