日本各地に祀られている神様のご紹介。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
古くから日本の各地ではそれぞれに雨乞いの神様。
あるいは治水(灌漑)の神様として水の神が祀られてきた。
タカオカミ神の素顔とは、そうした名もない数多くの水の神そのものであるといえる。
水の神といっても、その機能や役割によって水田の灌漑用水の神、飲料水をつかさどる井戸の神漁業や水運業の神、火除けの神などに大別することができる。
そのなかで、タカオカミ神が本来専門とするのは、有力な雨乞いの神、治水の神の機能である。
さらに具体的にいえば、農耕生産、とりわけ稲作に深く関係する雨水の神として、水田に利用される川の水をつかさどる女神ということになる。
朝廷の篤い崇敬を受けて霊威を発揮。
全国に広がるタカオカミ神を祀る神社の本源は、京都の貴船神社である。
同社は奈良県の丹生川上神社と並んで、古くから朝廷の篤い崇敬を受け、祈雨・祈晴の神として農業に霊威を発揮したほか、醸造、染色、料理飲食、浴場など、業種の関係者の信仰も集めてきた。
なお、京都の貴船神社の祭神としてのタカオカミ神(貴船神)は、平安時代の宮廷の女流歌人和泉式部のエピソードにちなんで男女の縁切り・縁結びをつかさどる霊力を発揮する恋の女神として人気がある。
鎮座地:貴船神社(京都市左京区鞍馬貴船町)
あるいは治水(灌漑)の神様として水の神が祀られてきた。
タカオカミ神の素顔とは、そうした名もない数多くの水の神そのものであるといえる。
水の神といっても、その機能や役割によって水田の灌漑用水の神、飲料水をつかさどる井戸の神漁業や水運業の神、火除けの神などに大別することができる。
そのなかで、タカオカミ神が本来専門とするのは、有力な雨乞いの神、治水の神の機能である。
さらに具体的にいえば、農耕生産、とりわけ稲作に深く関係する雨水の神として、水田に利用される川の水をつかさどる女神ということになる。
朝廷の篤い崇敬を受けて霊威を発揮。
全国に広がるタカオカミ神を祀る神社の本源は、京都の貴船神社である。
同社は奈良県の丹生川上神社と並んで、古くから朝廷の篤い崇敬を受け、祈雨・祈晴の神として農業に霊威を発揮したほか、醸造、染色、料理飲食、浴場など、業種の関係者の信仰も集めてきた。
なお、京都の貴船神社の祭神としてのタカオカミ神(貴船神)は、平安時代の宮廷の女流歌人和泉式部のエピソードにちなんで男女の縁切り・縁結びをつかさどる霊力を発揮する恋の女神として人気がある。
鎮座地:貴船神社(京都市左京区鞍馬貴船町)
PR
日本の水の女神を代表する実力派。
タカオカミ神は、日本神話に登場する女神で、全国に広がる貴船神社(総本社は京都の貴船神社)の祭神であることから、貴船神とも呼ばれてその名を知られている、代表的な水の女神である。
水の神は、女性と決まっているわけではないが、日本の場合は女神としてイメージされる場合が多い。
古来、水にかかわる神霊の代表格といえば龍蛇神である。
民話や民間信仰でもおなじみの龍や蛇は水の精霊であったり、水をつかさどる神霊の化身であったりする。
こうして龍や蛇は、農耕と深くかかわる豊穣の大地母神として信仰されてきた。
そこからの連想として、女神のイメージが形成されたと考えられる。
飛び散る火の神の血から化成。
日本神話では、「神生み」の物語の最後にイザナギ命が火の神カグツチの首をバッサリと断ち斬ったとき、流れた鮮血から化成した水の神であるとされている。
『古事記』や『日本書紀』一書第六には、イザナギ命が火の神カグツチの首を斬ったときに、飛び散った血からクラオカミ神が生まれたとあり、また『日本書紀』一書第七にはタカオカミ神が生まれたとある。
名義について考えてみると、タカオカミの「高」は高い峰・天の高みといった意味で、そこにあって雨水をつかさどる神としての雷神が思い浮かぶ。
一方クラオカミの「闇(くら)」は、鬱蒼とした緑に覆われ、昼なお暗い渓谷を連想させ、峰から下る
渓流に宿る水神という性格がうかがわれる。
山に降った雨は、谷を下って川となり、野を潤すという意味で、二神を合わせて源流の神と考えることができる。
「龗(おかみ)」とは、雨(水)をつかさどる龍神のことである。
タカオカミ神は、クラオカミ神と一緒に神社の祭神とされていたり、あるいは二神を総称した「淤加美神(おかみのかみ)」の名で祀られている場合もある。
タカオカミ神は、日本神話に登場する女神で、全国に広がる貴船神社(総本社は京都の貴船神社)の祭神であることから、貴船神とも呼ばれてその名を知られている、代表的な水の女神である。
水の神は、女性と決まっているわけではないが、日本の場合は女神としてイメージされる場合が多い。
古来、水にかかわる神霊の代表格といえば龍蛇神である。
民話や民間信仰でもおなじみの龍や蛇は水の精霊であったり、水をつかさどる神霊の化身であったりする。
こうして龍や蛇は、農耕と深くかかわる豊穣の大地母神として信仰されてきた。
そこからの連想として、女神のイメージが形成されたと考えられる。
飛び散る火の神の血から化成。
日本神話では、「神生み」の物語の最後にイザナギ命が火の神カグツチの首をバッサリと断ち斬ったとき、流れた鮮血から化成した水の神であるとされている。
『古事記』や『日本書紀』一書第六には、イザナギ命が火の神カグツチの首を斬ったときに、飛び散った血からクラオカミ神が生まれたとあり、また『日本書紀』一書第七にはタカオカミ神が生まれたとある。
名義について考えてみると、タカオカミの「高」は高い峰・天の高みといった意味で、そこにあって雨水をつかさどる神としての雷神が思い浮かぶ。
一方クラオカミの「闇(くら)」は、鬱蒼とした緑に覆われ、昼なお暗い渓谷を連想させ、峰から下る
渓流に宿る水神という性格がうかがわれる。
山に降った雨は、谷を下って川となり、野を潤すという意味で、二神を合わせて源流の神と考えることができる。
「龗(おかみ)」とは、雨(水)をつかさどる龍神のことである。
タカオカミ神は、クラオカミ神と一緒に神社の祭神とされていたり、あるいは二神を総称した「淤加美神(おかみのかみ)」の名で祀られている場合もある。
宗像三女神のなかでも、とりわけ美人とされて人気抜群なのがイチキシマヒメ命である。
なぜそうなのかといえば、その最大の理由は、神仏習合によって妖艶な弁才天と合体したことである。
両者を結びつけたキーワードは、まさに「美しい水の女神」というものである。
そもそも弁才天は、インドのヒンドゥー教の河の神で、財宝・美・音楽・芸能などをつかさどるとされていたが、奈良時代に日本に入ってきてからは、民間信仰の水神信仰とも融合して、水の神、農業神としても広く祀られるようになった。
とくに中世以降は、琵琶を奏でる妖艶な姿の像が弁天社に祀られ、音楽や芸術の才能上達、弁舌や知識(知恵)の神として信仰が広がった。
同時に人々を魅了したのが、縁結びや財宝をもたらす金運の女神としての信仰である。
そうした財宝神としての人気の高まりを受けて名前も「弁財天」と書かれるようになり、神仏混淆の時代には宗像・厳島系神社の多くがイチキシマヒメ命を弁財天として祀るという現象も起きた。
なお、各地にある弁天社が水辺に祀られているのは、海の神・水の神という女神の基本的な性格が深く関係しているのである。
鎮座地:宗像大社(福岡県宗像市田島)
なぜそうなのかといえば、その最大の理由は、神仏習合によって妖艶な弁才天と合体したことである。
両者を結びつけたキーワードは、まさに「美しい水の女神」というものである。
そもそも弁才天は、インドのヒンドゥー教の河の神で、財宝・美・音楽・芸能などをつかさどるとされていたが、奈良時代に日本に入ってきてからは、民間信仰の水神信仰とも融合して、水の神、農業神としても広く祀られるようになった。
とくに中世以降は、琵琶を奏でる妖艶な姿の像が弁天社に祀られ、音楽や芸術の才能上達、弁舌や知識(知恵)の神として信仰が広がった。
同時に人々を魅了したのが、縁結びや財宝をもたらす金運の女神としての信仰である。
そうした財宝神としての人気の高まりを受けて名前も「弁財天」と書かれるようになり、神仏混淆の時代には宗像・厳島系神社の多くがイチキシマヒメ命を弁財天として祀るという現象も起きた。
なお、各地にある弁天社が水辺に祀られているのは、海の神・水の神という女神の基本的な性格が深く関係しているのである。
鎮座地:宗像大社(福岡県宗像市田島)
もともと宗像三女神は、北九州地方の筑紫の国を基盤とする海女集団の宗像君の信望する海の神であった。
そんな地方神としての海の神が大いに霊威を発揮して神威を高めたのは、朝鮮半島や中国大陸との交流が盛んになる4世紀末頃である。
九州と朝鮮半島の間にある玄界灘は、常に危険をはらむ荒海である。
そのため朝鮮半島へ向かう大和朝廷の使者は、海路の玄関口に鎮座する宗像三女神に奉幣し
航路の安全を祈願した。
こうして中央の大和政権と結びつくことによって国家神となり、日本を代表する海の神となったのである。
宗像三女神を信望していた宗像君一族は、そもそも航海を得意とする外洋航路型・海外志向型の海女族だったという研究者の説もある。
そうした要素も踏まえて、この女神の役割をひと言でいえば「古代の国際交流の守神」といった側面をもっていたといえる。
また、その霊威は古来、道の神として信仰され、大陸に渡った遣唐使なども出航の前に
必ず交通安全を祈願したのである。
そんな地方神としての海の神が大いに霊威を発揮して神威を高めたのは、朝鮮半島や中国大陸との交流が盛んになる4世紀末頃である。
九州と朝鮮半島の間にある玄界灘は、常に危険をはらむ荒海である。
そのため朝鮮半島へ向かう大和朝廷の使者は、海路の玄関口に鎮座する宗像三女神に奉幣し
航路の安全を祈願した。
こうして中央の大和政権と結びつくことによって国家神となり、日本を代表する海の神となったのである。
宗像三女神を信望していた宗像君一族は、そもそも航海を得意とする外洋航路型・海外志向型の海女族だったという研究者の説もある。
そうした要素も踏まえて、この女神の役割をひと言でいえば「古代の国際交流の守神」といった側面をもっていたといえる。
また、その霊威は古来、道の神として信仰され、大陸に渡った遣唐使なども出航の前に
必ず交通安全を祈願したのである。
宗像三女新は、各地の宗像・厳島系の神社に祀られている。
その総本社が『古事記』にも記されている福岡県宗像市の宗像大社である。
九州と朝鮮半島を結ぶ玄界灘のほぼ中央に浮かぶ沖ノ島の沖津ぐうに、タギリヒメ命。
沖ノ島と陸との中間にある大島の中津宮にタキツヒメ命。
陸の辺津宮にイチキシマヒメ命がそれぞれ祀られていて、この三宮をあわせたものが宗像大社であり、一般には宗像神と呼ばれている。
神名の「タギリ」や「タキツ」は、潮流の速く激しい要素を表わしたもので「イチキシマ」は「神霊を斎祀る島」という意味である。
その名で呼ばれるイチキシマヒメ命は、平家の崇敬を受けた通称”安芸の宮島”として有名な厳島神社(広島県廿日市市)の祭神にもなっていて、神社の名前もこの女神に由来するといわれている。
全国各地に広がっている宗像・厳島系の神社はほとんどがこの両社から分霊されたものである。
その総本社が『古事記』にも記されている福岡県宗像市の宗像大社である。
九州と朝鮮半島を結ぶ玄界灘のほぼ中央に浮かぶ沖ノ島の沖津ぐうに、タギリヒメ命。
沖ノ島と陸との中間にある大島の中津宮にタキツヒメ命。
陸の辺津宮にイチキシマヒメ命がそれぞれ祀られていて、この三宮をあわせたものが宗像大社であり、一般には宗像神と呼ばれている。
神名の「タギリ」や「タキツ」は、潮流の速く激しい要素を表わしたもので「イチキシマ」は「神霊を斎祀る島」という意味である。
その名で呼ばれるイチキシマヒメ命は、平家の崇敬を受けた通称”安芸の宮島”として有名な厳島神社(広島県廿日市市)の祭神にもなっていて、神社の名前もこの女神に由来するといわれている。
全国各地に広がっている宗像・厳島系の神社はほとんどがこの両社から分霊されたものである。

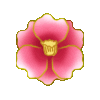
 カレンダー
カレンダー