日本各地に祀られている神様のご紹介。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
『日本書紀』が伝えるヤマトトトヒモモソヒメ命の性格は、神の言葉を伝える神妻、つまり神が憑依する巫女である特殊な霊的能力を備えた預言者的巫女といってもいいだろう。
その性格を示す話が『日本書紀』崇神(すじん)天皇の条に記されている。
崇神天皇の治世に、全国に疫病が流行して田畑は荒れ民が飢えに苦しんでいた。
災厄の原因を天皇が占うと、徳の高い神がヤマトトトヒモモソヒメ命に神懸りして、「われを大切に祀れば国は自然に平穏になるだろう」と託宣し、天皇が名を問うと「大和国のオオモノヌシ神なり」と答えた。
信託に従って、天皇が大三輪氏の祖・大田田根子を祭主として手厚く祀ったところ、たちまち国の災いは鎮まったという。
『日本書紀』にはまた、「崇神天皇の伯母・ヤマトトトヒモモソヒメ命は聡明でよく物事を予知された」とある。
その例として、孝元天皇の皇子タケハニヤスヒコ命が謀反を計画したとき、神の化身である少女の歌に凶兆を察知し、いち早く天皇に告げたことで反乱を防いだと伝えられている。
こうした預言者的巫女のイメージは、国の政治を左右する力を発揮した卑弥呼や、神巧(じんぐう)皇后といった女性の姿を連想させる。
鎮座地:吉備津神社(岡山県吉備津)
その性格を示す話が『日本書紀』崇神(すじん)天皇の条に記されている。
崇神天皇の治世に、全国に疫病が流行して田畑は荒れ民が飢えに苦しんでいた。
災厄の原因を天皇が占うと、徳の高い神がヤマトトトヒモモソヒメ命に神懸りして、「われを大切に祀れば国は自然に平穏になるだろう」と託宣し、天皇が名を問うと「大和国のオオモノヌシ神なり」と答えた。
信託に従って、天皇が大三輪氏の祖・大田田根子を祭主として手厚く祀ったところ、たちまち国の災いは鎮まったという。
『日本書紀』にはまた、「崇神天皇の伯母・ヤマトトトヒモモソヒメ命は聡明でよく物事を予知された」とある。
その例として、孝元天皇の皇子タケハニヤスヒコ命が謀反を計画したとき、神の化身である少女の歌に凶兆を察知し、いち早く天皇に告げたことで反乱を防いだと伝えられている。
こうした預言者的巫女のイメージは、国の政治を左右する力を発揮した卑弥呼や、神巧(じんぐう)皇后といった女性の姿を連想させる。
鎮座地:吉備津神社(岡山県吉備津)
PR
死んだヤマトトトヒモモソヒメ命は、のちに「昼は人間がつくり、夜は神が作った」と伝わる立派な墓に葬られ。
当時の人々はそれを箸墓と呼んだという。
その墓と伝わるのが、奈良県桜井市にある日本で最も古い巨大古墳(全長約280メートル)の箸墓古墳である。
いまだ未発掘のこの古墳は、古代の邪馬台国の女王卑弥呼の墓ではないかともいわれて歴史ロマンを募らせる史跡である。
ヤマトトトヒモモソヒメ命の死を招いた箸と「ホト(女陰)」について考えてみると、日本神話のなかでは、ほかにも機織の杼(ひ)でホトを突いて死ぬ機織女(はたおりめ)や、ホトを見せることで目の前の障害を取り除いて道を切り開く女神(アメノウズメ命)などが登場する。
いずれも太陽神アマテラス大神に深く関係する存在であり、その意味でこの女神には、日の神を祀る巫女としての性格もうかがえるのである。
当時の人々はそれを箸墓と呼んだという。
その墓と伝わるのが、奈良県桜井市にある日本で最も古い巨大古墳(全長約280メートル)の箸墓古墳である。
いまだ未発掘のこの古墳は、古代の邪馬台国の女王卑弥呼の墓ではないかともいわれて歴史ロマンを募らせる史跡である。
ヤマトトトヒモモソヒメ命の死を招いた箸と「ホト(女陰)」について考えてみると、日本神話のなかでは、ほかにも機織の杼(ひ)でホトを突いて死ぬ機織女(はたおりめ)や、ホトを見せることで目の前の障害を取り除いて道を切り開く女神(アメノウズメ命)などが登場する。
いずれも太陽神アマテラス大神に深く関係する存在であり、その意味でこの女神には、日の神を祀る巫女としての性格もうかがえるのである。
三輪山神婚伝説のヒロイン。
ヤマトトトヒモモソヒメ命という長い名前に関しては、一説に「多くの魂が鳥のように飛んでいくことを喩えたもの」という解釈があり、固有名詞ではなく、古代の神祭りの司祭役の巫女などの役割を指す一般名詞ではないかとも考えられている。
しかし、確かなことは不明である。
この女神は、第七代孝霊天皇の娘で、有名な話として蛇体のオオモノヌシ神の妻になったという
三輪山伝説がある。
妻となったヤマトトトヒモモソヒメ命のもとに通う三輪山の神・オオモノヌシ神は、いつも昼間は
姿を見せず夜になると現れた。
あるとき、不満を募らせた姫が「夜に来てすぐに帰ってしまうので、はっきりとお顔を見ることができません。どうかゆっくりと朝まで留まってください」と頼んだ。
すると、オオモノヌシ神は「よし、わたしは明日の朝おまえの櫛箱に入っていることにしよう。わたしの姿を見ても決して驚いてはいけない」と答えた。
翌朝、姫が櫛箱を開けてみると、そこにはうるわしい小さな蛇が入っていた。
驚いた姫が思わず叫び声をあげると、青年の姿に戻ったオオモノヌシ神が「おまえはわたしに恥をかかせた!」と言い捨てて三輪山へと飛び去った。
それを見送って、後悔の念に襲われた姫はその場にしゃがみこんだ。
その拍子に箸が陰部に突き刺さって死んでしまった。
ヤマトトトヒモモソヒメ命という長い名前に関しては、一説に「多くの魂が鳥のように飛んでいくことを喩えたもの」という解釈があり、固有名詞ではなく、古代の神祭りの司祭役の巫女などの役割を指す一般名詞ではないかとも考えられている。
しかし、確かなことは不明である。
この女神は、第七代孝霊天皇の娘で、有名な話として蛇体のオオモノヌシ神の妻になったという
三輪山伝説がある。
妻となったヤマトトトヒモモソヒメ命のもとに通う三輪山の神・オオモノヌシ神は、いつも昼間は
姿を見せず夜になると現れた。
あるとき、不満を募らせた姫が「夜に来てすぐに帰ってしまうので、はっきりとお顔を見ることができません。どうかゆっくりと朝まで留まってください」と頼んだ。
すると、オオモノヌシ神は「よし、わたしは明日の朝おまえの櫛箱に入っていることにしよう。わたしの姿を見ても決して驚いてはいけない」と答えた。
翌朝、姫が櫛箱を開けてみると、そこにはうるわしい小さな蛇が入っていた。
驚いた姫が思わず叫び声をあげると、青年の姿に戻ったオオモノヌシ神が「おまえはわたしに恥をかかせた!」と言い捨てて三輪山へと飛び去った。
それを見送って、後悔の念に襲われた姫はその場にしゃがみこんだ。
その拍子に箸が陰部に突き刺さって死んでしまった。
ミズハノメ神を祭神とする代表的な神社は奈良県の丹生川上神社中社である。
当社は、タカオカミ神を祀る京都の貴船神社と並ぶ有力な水の神として古くから朝廷の崇敬を受けきた。
この女神の霊威が広く世に広まり、民間信仰の井戸神として浸透した背景にはそういう歴史も秘められているのである。
ミズハノメ神は、また紙すき神という性格ももっていて、今日では製紙業の守護神という顔でも知られている。福井県の越前市の大滝神社摂社・岡太神社の社伝では、昔、この地に美しい乙女の姿をした水の神が現れて、紙すきの方法を教えた。
村人が神の名を聞くと「川の上流にすみミズハノメ神なり」といって姿を消したという。
以来、この地で作られるようになったのが越前和紙だという。
鎮座市:丹生川上神社中社(奈良県吉野郡東吉野村)
当社は、タカオカミ神を祀る京都の貴船神社と並ぶ有力な水の神として古くから朝廷の崇敬を受けきた。
この女神の霊威が広く世に広まり、民間信仰の井戸神として浸透した背景にはそういう歴史も秘められているのである。
ミズハノメ神は、また紙すき神という性格ももっていて、今日では製紙業の守護神という顔でも知られている。福井県の越前市の大滝神社摂社・岡太神社の社伝では、昔、この地に美しい乙女の姿をした水の神が現れて、紙すきの方法を教えた。
村人が神の名を聞くと「川の上流にすみミズハノメ神なり」といって姿を消したという。
以来、この地で作られるようになったのが越前和紙だという。
鎮座市:丹生川上神社中社(奈良県吉野郡東吉野村)
ミズハノメ神は、タカオカミ神とともに日本の代表的な水の神である。
神話には治水の神として登場するが、民間信仰では井戸・水道の神としての性格が中心になって、日常のなかで広く信仰されている。
水の神というと民俗信仰の世界では龍や蛇の姿をとるが、その一方では清らかなイメージの女性神という印象も強い。
それを象徴するのがこのミズハノメ神で人間の前に現れるときには、うるわしい乙女の姿としていると考えられている。
そもそも水は、人間の生命の源である。
水のもつパワーは、農業、漁業、工業、交通、あるいは健康、レジャーなど、人間の生活のあらゆる場面で発揮されている。
とくに、ミズハノメ神の場合は、安産の神でもあるとともに農耕との関係が深い。
その理由は、この神が大地母神であるイザナミ命の尿から生まれたことにある。
イザナミ命の尿から化生。
日本神話では、代表的な水の女神は、その誕生から火と密接に関係している。
『古事記』には、前項で紹介したタカオカミ神が火の神カグツチの血から生まれたとされているが、このミズハノメ神の場合は、イザナミ命が火の神カグツチを生むときに陰部を焼かれ、病み苦しんでいるときに漏らした尿から生まれた女神とされている。
神の名の「ミズハ」には、「水つ走」「水が這う」という意味があり、おそらく蛇のように身をくねらせて流れる下る川からイメージされたものだろう。
あるいは「水つ早」と解して、水の湧き出るもと(泉、井戸)という意味も考えられている。
火は、古くから食物生産にかかわる一種の産霊(むすび)としての性格をもっていたことが、神話でミズハノメ神とともに食物神が生まれることからもうかがえる。
さらに、糞尿は昔から大切な有機肥料であった。
そこから大地母神であるイザナミ命の尿から生まれたこの女神は、肥料の神、有機農法の神とも考えられるわけである。
神話には治水の神として登場するが、民間信仰では井戸・水道の神としての性格が中心になって、日常のなかで広く信仰されている。
水の神というと民俗信仰の世界では龍や蛇の姿をとるが、その一方では清らかなイメージの女性神という印象も強い。
それを象徴するのがこのミズハノメ神で人間の前に現れるときには、うるわしい乙女の姿としていると考えられている。
そもそも水は、人間の生命の源である。
水のもつパワーは、農業、漁業、工業、交通、あるいは健康、レジャーなど、人間の生活のあらゆる場面で発揮されている。
とくに、ミズハノメ神の場合は、安産の神でもあるとともに農耕との関係が深い。
その理由は、この神が大地母神であるイザナミ命の尿から生まれたことにある。
イザナミ命の尿から化生。
日本神話では、代表的な水の女神は、その誕生から火と密接に関係している。
『古事記』には、前項で紹介したタカオカミ神が火の神カグツチの血から生まれたとされているが、このミズハノメ神の場合は、イザナミ命が火の神カグツチを生むときに陰部を焼かれ、病み苦しんでいるときに漏らした尿から生まれた女神とされている。
神の名の「ミズハ」には、「水つ走」「水が這う」という意味があり、おそらく蛇のように身をくねらせて流れる下る川からイメージされたものだろう。
あるいは「水つ早」と解して、水の湧き出るもと(泉、井戸)という意味も考えられている。
火は、古くから食物生産にかかわる一種の産霊(むすび)としての性格をもっていたことが、神話でミズハノメ神とともに食物神が生まれることからもうかがえる。
さらに、糞尿は昔から大切な有機肥料であった。
そこから大地母神であるイザナミ命の尿から生まれたこの女神は、肥料の神、有機農法の神とも考えられるわけである。

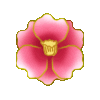
 カレンダー
カレンダー